今回は、マーケティングに限らずあらゆる職種で生じる「属人化」という根深い問題について論じたいと思います。なぜそもそも人は仕事を属人化させてしまうのか。なぜ属人化がいけないのか。そしてどう解消すれば良いのか、フレームワークを交えながらご説明します。
属人化とは、「情報」と「業務」の独占
仕事を自分に属人化させている人は、情報と業務を自分で独占したがる傾向にあります。
独占している情報は、社内の内部事情、社外のノウハウ、世の中一般的な知識まで、多岐に渡ります。その人がコネを築いて、情報をかき集めて、そして勉強してきたものですので、そのこと自体は褒めてしかるべきものです。
独占している業務は、奥義のようなもので、長年の修行の末に身につけたものです。それまで誰もやりたがらなかった仕事を周りから押し付けられて、苦労して、努力して習得したというケースが多いように思います。
しかし、会社員である以上、その情報やノウハウは社内の資産として共有できる状態にしてほしいものです。しかし、彼らはその情報や業務を手放しません。
そもそも、なぜ人は仕事を属人化させたがるのか
どうして人は情報や業務を自分に属人化させたがるのでしょうか。その原因を考えてみると、以下のような要因が推測されます。
社内の色々な人が頼ってくれるから
自分に色々な情報や業務が属人化しているので、社内の様々な立場の人から頼ってもらうことができます。人に頼られるのは、大きな喜びを得られる体験です。
「こんなことに困っていて」と相談されて、そのお困りごとをパパッと解決してあげると、自分は仕事ができて人の役に立っていると言う「錯覚」に陥りがちです。人の役にたつ仕事ができている以上、役立たずのレッテルを貼られる心配や、自分の仕事がなくなってしまう心配をする必要はないでしょう。
色々な情報が自分に集まるから
属人化している担当者を頼る人には、様々な立場の人がいます。中には、社内の役職者や大きな権限を持つ人もいるでしょう。役職者が相談してくるときは、多くの人が知ることのできない社内の内部事情が「おまけ」としてついてきます。

今度会計基準を変えようと思っているんだけれど、今の経理システムって対応できるのかな?
こんな形で「会計基準が変わるらしい」という重要情報を手に入れることができるのです。
担当者は、この質問に答えてあげる代わりに、「会計基準を変えようとしているらしい」というビッグニュースを手に入れることができます。
権力・判断権限が自然と手に入るから
属人化によりますます多くの情報が自分に集まるようになることで、周囲との情報格差が生まれ、その人は大きな権限を手に入れます。情報は多く持っていると、様々な意思決定や判断の権限も持てるようになります。
なぜなら、担当者は決裁者に提供する情報をコントロールし、自分が良いと考える方向に物事を誘導することができるからです。いわゆる情報の非対称性の問題が起きてきますので、決裁者の判断は、担当者にとって都合の良い情報に基づき行われることになります。
自分の仕事がなくなることが怖いから
仕事を属人化させたがる人は、往々にして自分に自信がない傾向があります。内心、仕事がなくなるんじゃないか、あるいは、仕事を取られちゃうんじゃないかと、日々恐怖を感じながら暮らしているのです。
その結果として、属人化がおきます。情報は当然周りに公開しません。「こんな資料ないかな?」と聞いても、何かと理由をつけて、最小限の情報だけを開示してきます。
属人化のデメリット
属人化そのものは悪いことではありません。「専門的」であることと「属人的」であることは表裏一体です。最新の情報をいつも収集しており、その結果として周囲から頼られる、あるいは一定の判断権限を持つことは、むしろ模範的なサラリーマンのあり方なのかもしれません。
問題は、それを自分にため込もうとする姿勢です。情報を開示しない属人化の姿勢には、以下のようなデメリットがあります。
会社と個人の成長機会を奪う
会社全体で見たときに、専門性のある人は、一人より二人、二人より三人いた方が望ましいです。しかし、属人化によって情報を開示されないため、専門性がある人は一人のままです。担当者間での相互作用が起きないので、これでは、会社という組織を形成している意味がありません。
会社の継続性リスクと個人の過労リスク
会社運営上欠かせない業務が属人化していると、突然の退職や病気によって会社運営に支障をきたしてしまうかもしれません。たとえば、会計業務が特定の方に属人化していると、その方がいなくなることで決算すら正しくできなくなってしまうかもしれません。取引先への請求や入金確認業務が属人化していると、その担当者が突如いなくなることによって資金繰りがショートしてしまうかもしれません。
属人化そのものがこの退職や病気を誘発するという側面もあります。「この業務はあの人しかできないから」と言う理由で特定の業務を一人に押し付け続けることで、過労状態となり、その結果としての退職や休職が発生してしまうかもしれません。
ミスの隠蔽リスク
属人化によって、担当者がミスを隠蔽することは極めて容易です。ミスを発見することは専門的な知識や長年の経験からくる勘が重要です。そんなものを周りの社員は持ち合わせてはいないので、極めて大きなリスクであると言えます。
属人化をいかに解消するか
実はこの属人化問題ですが、「ナレッジマネジメント」の分野ですでに先人たちが色々な研究をしています。ナレッジマネジメントとは、企業の中のノウハウをどうやって可視化し、共有するかという研究分野で、その中でも特にSECIモデルというものが有名です。
SECIモデルとは
SECIモデルは、組織のノウハウをどうやって可視化するか(暗黙知をどのように形式知にするか)を明らかにしたものです。組織内に存在する暗黙知と形式知が、その組織の中で変換し続けているという知識移転のプロセスを表現したものです。
SECIモデルは野中郁次郎・竹内弘高によって発表された「知識創造企業」の中で提唱された概念です。
興味深いのは、組織の中に存在する全ての知の源泉は、個々人の体験に基づく暗黙知であると指摘されている点です。つまり、個人レベルの「暗黙知」が属人化だと定義するならば、あらゆる知的創造は属人化から始まるという解釈ができるのではないでしょうか。
そして、その「暗黙知」をいかに「形式知」に変換していくのか、そのプロセスがSECIモデルでは解明されています。SECIモデルは、共同化・表出化・連結化・内面化の4つのステップでそのプロセスを分析します。
出典:知的創造企業
共同化
共同化で重要なのは、複数人で経験を共有するというプロセスです。何を属人化しているのかを尋ねて、話してもらう必要があります。その方法はいくつかありますが、手っ取り早いのは、若手をベテラン担当者につけることでしょう。
お金があればコンサルタントを入れるのも検討の価値があります。熟練のコンサルタントはその担当者が属人化させている業務内容を解明する術を持ち合わせており、何を聞けばいいのかの勘所も踏まえているので、品質の高いヒアリングが期待できます。
属人化を好む人は情報や業務を公開するのを嫌がります。そのため、もしかすると若手をつけてもコンサルタントを入れても業務内容を教えてくれないかもしれません。その場合、荒療治ですが、配置転換を命じるのも一つの方法です。配置転換を命じることで、強制的な「業務の引き継ぎ」が発生しますので、自ずと属人化していたノウハウも明らかになります。
表出化
マニュアルを作る作業になります。
「共同化」の過程でコンサルタントを入れているならば、ここも外注してしまえば楽をすることができます。しかし、その代償として数百万かかることは覚悟しておいた方が良いかもしれません。
連結化
複数のマニュアルを体系化することで仕事の全体像そつかむことができるようになります。
一つ一つのマニュアルをただ並べるのではなく、それぞれのマニュアル(=業務)がどういった関係性にあるのかを解説するのも、属人化解消のための重要なプロセスになります。
内面化
作ったマニュアルに基づき、実践していく過程になります。このプロセスが完了したら、ようやく属人化が解消したと言えるようになります。
いかに属人化された仕事を「共同化」させるかが肝心
ここまで属人化が起きる理由とそのデメリット、そして解消方法を考えてきました。
SECIモデルで解説した通り、いかに属人化した仕事を「共同化=複数人で経験を共有」させるかが肝心です。その「共同化」の手段として、以下をあげました。
ぜひ参考にして、業務の円滑化を図ってください。
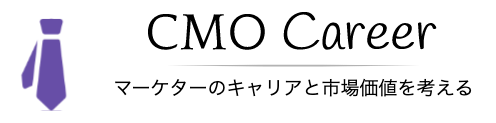



コメント